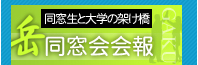みなさんこんにちは!学生レポーターの小林です。
そこで前期の大学生活、実践活動を紹介します。
過去にレポートしたものもあると思いますが、まとめとして読んでいただけると幸いです。
大学生活:
講義は実践的なもの(グループワークでの企画立案)とレクチャーで聞いているものの2つがありました。1つ日本の講義との違いを感じたことは、学生の積極性です。教授が解説をしている時に質問や言いたいことがある場合は、実際に発言する人が多いです。全員が積極的ではありませんが、私が受けてきた日本の講義と比べると、より賑やかな講義でした。また、一つの課題に時間をかけずどんどん先に進んでいきます。講義内容に大きな違いはないと思いますが、課題の捉え方や時間の使い方に違いを感じました。日本でやってきた内容もたくさんありました。私は、学習した内容を英語でより実践的な形で再学習し、自分のキャリアに繋げたくて留学をしています。時間がかかる方法ですが自分には長期的なプランのほうがあっていると感じています。
また、グループワークでプロジェクトを構築することができたことは自分の成長につながったと思います。自分を含め4人のグループでいろいろなことを経験できました。ものの見方や表現の仕方が違うコミュニティの中で1つの作品を作り上げることは、非常に難しいことでした。その中で、データなどの共通理解のできるものを使って話を進めていくことが最も早く効率的だと感じました。講義は、教授の説明する内容だけでなく活動自体に学ぶことが多いです。春学期でも多くの発見を期待しています。

実践活動:
実践活動としては、2つ紹介します。1つは、ラトビア国立図書館での日本文化教室です。月に1度程度、リガの大学で日本語を勉強している生徒たちが日本語、日本文化の学習機会として参加しています。もう一つは、企業訪問です。パリとチューリッヒにて3人の日本人駐在員と話すことができました。訪問のお願いをするところから実際に訪問をするまで、すべての過程を自分ですることは大きな経験になりました。また、深い知識や多く経験をしてきた人たちの話を聞くことができ、駐在の難しさや大変さを感じることができました。将来的に海外で働くビジョンを持っていたので、とても参考になる取り組みになったと思います。

人文社会科学部経済学科 小林
皆さんこんにちは!学生レポーターの小林です。
明けましておめでとうございます。
本年も、レポートを続けて投稿しますので引き続きよろしくお願いします!
今回は、年越しの話をします。

今年は友人と旧市街に行って年越しをしました。
旧市街のスクエアではライトアップと多くのDJが参加し、街中が盛り上がっていました。
クリスマスに引き続きクリスマスマーケットも年内はやっていたので、食事やドリンクで温まりながらカウントダウンを楽しめます。
年越しのタイミングでは花火と国歌の演出がありました。


自分は基本的に家族と過ごすことが多いので、久しぶりの花火を楽しめました。
現在のリガはとても寒いです。週によっては日中でも-20度くらいなのでなるべく中で過ごすようにしています。
年越しのタイミングは-5度くらいだった気がします。
室内でも言語学習や寮内での交流など、できることはいくらでもあるので充実してよい時間を過ごせています。
帰国まであと半年となり、時が過ぎるのはあっという間だなと感じるばかりです。
また来月からの新学期では新しい出会いもあると思うので楽しみにしています。
人文社会科学部経済学科(Faculty of engineering Economics and Management)小林
皆さんこんにちは!学生レポーターの小林です。
大学はテスト期間になり、勉強も少し忙しくなってきました。
先日行ったプロジェクトマネジメントと講義では、グループで3か月ほどかけて考えてきたビジネスの案をプレゼンしました。うまくまとめることができ、達成感を感じるプレゼンができました。もう少しテストがあるので頑張ります。
さて、今回はリガのクリスマスの話題です。
リガはクリスマスツリーの発祥地で有名です。500年前くらいの記録に残っているようです。
ヨーロッパはクリスマスマーケットが有名ですが、リガでもマーケットが出ています。



マーケットでは、ラトビアの名産品であるミトンやお土産、ホットワイン等を楽しむことができます。特にホットワインはみんなが飲んでいて、どの国でも親しまれているようです。

その他にも、子供たちが楽しめるような観覧車やメリーゴーランドなども設置され多くの人が楽しんでいます。ラトビア国外からの観光客も多く、リガの綺麗な街並みを見に来ているようです。

また、町全体がクリスマスライトで照らされているので普段暗いストリートなども明るく暖かい気持ちになります。
マーケットは12月いっぱいまでやっているので、ヨーロッパでのクリスマスをもう少し楽しみたいと思います。
それではメリークリスマス!
人文社会科学部経済学科 小林
静岡大学のホームページに「同窓生によるリレーエッセイ」のコーナーがあります。
今回は、岳陵会本部 委員 白鳥智香子様 (人文21回 社会学科卒)のエッセイが掲載されています。
皆様どうぞご覧ください。
HPはこちらから ↓ ↓
こんにちは!学生レポーターの小林です。
さて、前回の続きです。ヘルシンキはフィンランドの首都になります。
タリンから大きめのフェリーが出ていて、2時間海を渡りヘルシンキに向かうことができます。フェリーでは、食事、アルコール類、免税店など楽しむことができます。

ヘルシンキは自分にとって初めての北欧の国です。フィンランドといえば、サンタクロースやトナカイ、オーロラなどのイメージだと思いますが、ヘルシンキはかなり南に位置しているため普通に都会です。リガ、タリンと比べてもだいぶ都会だなと感じました。1つには北欧独特の建築デザインだと思います。変わったデザインの建物がたくさんありました。
ちなみに、ラップランドというスウェーデン、ノルウェー、ロシアにまたがっている地域は、サンタやオーロラを見ることができるようです。エラスムスグループがラップランド観光を提供しているので、そのうち行ってもいいかもしれません。信じられないくらい寒いらしいですが。
ヘルシンキでは、ヘルシンキ大聖堂、スオメンリンナの要塞、ウスペンスキー大聖堂、アテネウム美術館などに行ってきました。

ヘルシンキ大聖堂
入口の人を見ると分かりますが、かなり大きな建物でした。1840年くらいに建てられたようです。中は、大きなパイプオルガンが装飾されています。落ち着いた雰囲気の教会だと感じました。
ちなみに、この教会付近で日本人の旅行者がすりにあったようです。財布を取られたようなので、我々も気を引き締めました。観光地ではよく起こります。

アテネウム美術館
ヘルシンキ駅の正面にある美術館で、フィンランド出身のアーティストをはじめ多くの展示が行われています。モネ、ルノアールなどの有名な画家の作品を見ることができました。個人的には、この美術館とても楽しむことができました。
美術館は学生の場合割引されることがありますので、必ず申し出るようにしています。

スオメンリンナの要塞
ヘルシンキから20分ほどのところにある島です。過去に要塞として活躍したそうですが、現在では住民がおり、スーパーなどもあります。3時間ほどあれば島を一周できるかなと感じの大きさです。こちらから見るヘルシンキの町はとても綺麗です。

そして、たまたま満月を見ることができました。いい思い出です。

エストニア、フィンランドに行ってきましたが、どちらもとても気に入りました。両国とも一部しか見れていないので、将来的に他の都市にも行きたいと思わせてくれます。
海外でしかできない経験をできる限りしていきたいと思っています。
人文社会科学部経済学科(Faculty of Engineering Economics and Management)小林寛明