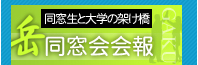静岡大学には1962(昭和37)年に、みんなが声を合わせてうたえる歌を持とうという願いのもと、作詞は当時文理学部2年髙嶋善二さん、作曲は石井歓さんによって誕生した学生歌「われら若人」があります。「静岡大学はひとつ」という思いと願いを込められた歌詞は、爽やかなメロディーとともに同窓生のみなさんにも親しまれております。このミュージックビデオは2019年、静岡大学の法人統合・大学再編の検討が進む中、当時人文社会科学部3年の佐々木勇輝さんが「静岡大学の仲間という存在やそのつながりを今一度、見つめ直そう」という思いから、静岡キャンパスと浜松キャンパスの学生に呼びかけ、学生有志によりみんなで歌う動画が制作、公開に至りました。(岳陵会は動画制作の協賛を学生支援として行いました)
静岡大学学生歌「われら若人」|静岡大学 (shizuoka.ac.jp)
記念事業の告知映像をアーカイヴとして公開いたします。
こちらをご覧になられて、静岡大学の同窓であることを改めて誇りに思ったという声も寄せられた大変好評の告知映像でした。ぜひご覧いただけますと幸いです。
本事業に携わった同窓生、関係者の皆様、ご来場くださった皆様に改めて心よりお礼申し上げます。
皆さんこんにちは!学生レポーターの小林です。
先日、エストニアのタリンとフィンランドのヘルシンキに行ってきたのでそのレポートをします。
今回は、タリン観光についてです。
リガからタリンはバスが出ていて、大体4時間くらいで到着します。バスは普通の深夜バスをイメージしてもらえるといいと思います。往復で5,000円くらいで購入できました。
到着すると10月にも関わらず、雪が積もっていました。リガも雪が降る日はあったのですが、タリンの道は凍っていて気を付けないと普通に転びます。幸い、転ばずに済みましたがほんとにつるつるでしたね。はじめに私たちは旧市街へ向かいました。

エストニアはラトビアの北側に位置しています。
寒いとは思っていましたが、日中晴れていても2~3℃ほどしかなく常に寒かったです。ちなみにリガもそうですが、大体毎日曇っています。おそらく天気の変化も頻繁なのだと思います。
ただ、雪のおかげできれいな景色を見ることができました。より冬っぽい雪景色はこれからの景色に見られるようです。とても綺麗ですが、寒いので冬に旅行する場合は、気を付けてください。

リガより赤い屋根が目立つような印象を受けました。



これは、テレビ塔からのタリンの様子です。写真を見ればわかると思いますが、やはり森、公園が多いです。自然の中に都市があるという感じです。

また、このように旧市街の中には城壁やお城の跡地が残っています。これらの歴史が街を明るく、鮮やかなものにしています。

コフトウッツァ展望台
タリン旧市街が一望できるスポットです。
エストニアはラトビア同様、日本人からするとあまり聞きなじみのない国かもしれません。
私はリガに来るまでは、人生でも行くことはないだろうなと思っていました。
ただ、来てみるといろいろな発見があります。高度電子国家と言われているだけあり、街は自動化されているものが多いです。
また、リガと似ていることもわかりました。やはり美しい街です。
いろいろな国へ行って、景色や文化をできる限り楽しんでいきたいと思わせてくれます。
タリンは、1、2日あれば楽しむことができると思います。次エストニアに来たときは、郊外へ行ってみたいと思います。
そして、エストニアからフェリーでフィンランドへ向かいます。
続きは次回のレポートで!
岳陵会ラウンジ、開催!
静岡大学人文社会科学部は、1922年に設立された旧制静岡高等学校を前身とし、100年を越える歴史を有する学部です。社会学、文学、法学、経済学という4つの学位が授与される、高い専門性を誇る教育機関として、数多くの優秀な卒業生が、個性と多様性を大切にする人文社会科学部の伝統のもと、静岡はもちろん日本各地そして世界で活躍しています。
人文社会科学部の同窓会である岳陵会は、同窓生と現役学生、教職員、地域の方々をつなぐ交流、懇親の場として「岳陵会ラウンジ」を開きます。ぜひご来場ください。
※大盛況で終了しました。ご来場くださった皆様に御礼申し上げます。
| 時間 | 2023/11/4(土) 12:00~16:00 |
| 2023/11/5(日) 10:00~16:00 | |
| 場所 |
静岡大学 人文社会科学部 B棟 2階 204・205教室 静岡県静岡市駿河区大谷(おおや)836 |
【特別展示企画】
① 静岡大学人文社会科学部大学アーカイヴズ 特別展示
~懐かしの木製標札から感じる静岡大学~
学部の前身である旧制静岡高等学校の創立から1968年の移転まで使用された校舎の資料、それらを引き継いだ静岡大学文理学部・人文学部に関係する資料など、全国的に見ても非常に珍しい資料が「学部大学アーカイヴズ委員会」で整理保存されています。
今回、1968年まで静岡市葵区大岩本町(現在の静岡市城北公園)にあった大岩校舎本館の正面玄関に掲げられていた文理学部・人文学部の木製標札を特別展示いたします。
あわせて昨年度の記念事業で作成され会場で反響が大きかった旧制静岡高等学校創立から本学部の歴史をまとめた写真パネルを展示いたします。この機会を通じて、静岡大学の魅力や歴史、伝統を感じつつ、皆様がご交流いただければと願っております。
(協力:人文社会科学部大学アーカイヴズ委員会・人文社会科学部教授 小二田誠二先生、人文社会科学部教授 戸部健先生)
② 静岡大学人文社会科学部×岳陵会 連携講座 企画展示
~いまこそ知ってほしい「わたしたちの静岡大学」PRポスター ~
岳陵会では人文社会科学部と協働して、本学部(文理・人文・人文社会科学部)卒業生が自らの学生時代や社会での経験や体験を踏まえた講演など、現代の学生がいま必要なキャリア形成を考えつつ学び、習得する場として連携講座を開講しており、例年人気の講座となっております。今年度も140名を超える受講生が学んでいますが、今年度、自らのキャリアともなる「わたしたちの静岡大学」について考え、本学部の社会、言語文化、経済、法の4学科、地域創造学環の学生と海外からの留学生の混合による20チームで、主体的かつ協働的な学びとしてグループワークを行い、学生が思いを込めてチームで作成したポスターを展示いたします。
「静岡大学」のいまを生きる学生たちの思いに触れてください。
(協力:人文社会科学部教授 鳥畑与一先生・企画:岳陵会役員 木下 学(人文29回言語文化卒)
③ 静岡大学吹奏楽団・静岡大学混声合唱団 記念演奏上映会
~「われらは静岡大学」 ~心ひとつに、伝統をつなぐ~
11:30~(5日のみ)、12:30~、13:30~、14:30~
※各回20分程度の予定です。映像の上映会です。座席に限りがございます。
静岡大学には1962(昭和37)年に、みんなが声を合わせてうたえる歌を持とうという願いのもと、作詞は本学部の前身である当時文理学部2年髙嶋善二さん、作曲は石井歓さんによって誕生した学生歌「われら若人」があります。「静岡大学はひとつ」という思いと願いを込められた歌詞は、爽やかなメロディーとともに卒業生のみなさんにも親しまれており、各種式典などでも演奏される静岡大学を象徴する曲です。
今回、2022年11月に旧制静岡高等学校創立100周年記念事業としてグランシップで開催された記念演奏会のうち、静岡大学吹奏楽団と混声合唱団によるコラボレーションステージを収録した映像を上映会としてご視聴になれます。学生歌「われら若人」のほか、旧制静岡高等学校代表寮歌「地のさゞめごと」など4曲を上映いたします。
全国の国立大学でも伝統ある吹奏楽団、混声合唱団として、静岡と浜松のキャンパスの学生が交流して活動し、各種コンクールでは優秀な成績を積み重ねていることで知られる吹奏楽団と混声合唱団がひとつになった、さわやか、はつらつの響きをお楽しみください。
(協力:静岡大学吹奏楽団・静岡大学混声合唱団)
④ 考える森の学び舎で、ノドもココロも潤そう!
~本学卒業生が活躍する企業の飲みものを嗜もう~
静岡が誇る、世界でも有名なラムネの会社、木村飲料。実は、本学部の卒業生である木村英文さん(人文11回経済卒)が代表を務める会社です。同級生の間では木村さんが静大祭でラムネ飲料を出していた思い出があるそうですが、木村飲料のラムネシリーズをお楽しみいただけます。あわせて、本学の卒業生が活躍する静岡の飲料メーカーの飲料や菓子もご用意してお待ちしております。
※提供にあたっては学生支援のためのドネーション(カンパ)にご協力をお願いしております。
※数量限定:売り切れの際はご容赦ください。
静岡キャンパスの最も上に位置し、天空の城といわれる風光明媚な人文社会科学部。
人文社会科学部の100年を超える伝統を感じて、心もおなかもまんぷくに!
人文社会科学部B棟2階の会場でお待ちしております!
主催 静岡大学岳陵会
協力 静岡大学人文社会科学部・静岡大学人文社会科学部大学アーカイヴス委員会・静岡大学吹奏楽団・静岡大学混声合唱団
静大フェスタ・キャンパスフェスタの情報はこちらから
↓ ↓
https://wwp.shizuoka.ac.jp/festa/shizu_outline/
こんにちは! 学生レポーターの小林です。
リガはすっかり寒くなってきました。
日中でも10℃くらいしかないので、コートを着始めています。来週は氷点下まで行くようです。今でもたまに氷の粒が降ってきますが。
現地の人たちも同じような格好なので、「やっぱり寒い地域に住んでいても寒いものは寒いんだな」と最近感じました。
さて、今回は自分が選んだ寮の紹介です。
なぜかというと、最近引っ越しをしたからです。
海外の大学へ留学する場合は、寮に住む、アパート、シェアハウスを探すなどいろいろあると思いますが自分は大学が提供している寮に住んでいます。
自分の心構えとしては、「2人以上と生活できる」、「共同のスペース(キッチンや談笑場など)がある」場所に住みたいと思っていました。
1. 以前の寮
もともとは大学、市内からバスで40分ほどの場所にあった寮にいました。
1960年代に建てられたようなので、全体的にかなり古いです。
私からしたらキッチンやバスルームはきれいではなく1年間過ごすのは大変だなと思っていました。(結局1か月ほどしか滞在しませんでした。)
二人部屋で、家賃は3万5000千円程度、水道光熱費、冷蔵庫、シーツが含まれています。
ウクライナとインドからの生徒が大部分を占めているような状態でした。
5階建ての建物で一つのフロアに30部屋ほどあります。
また、1フロアにキッチン、洗面台、トイレが2つずつあります。シャワールームは1階にあって、一度に10人くらいが使えます。
2. 現在の寮
こちらの寮は市内にあります。
1、2、3人部屋が選べて、部屋に人が少なくなるほど家賃が上がっていきます。
自分は2人部屋に住んでおり、オランダ人のルームメイトがいます。
家賃は5万円ほどです。寮内の設備は新しく、水道光熱費、冷蔵庫、シーツが家賃に含まれています。シャワーとトイレ、洗面台が各部屋にあるのが以前の寮との違いです。また、キッチンは10人くらいが使うと思いますが、テーブルがあるのでいろいろな人と話ができます。実際引っ越して2日目にはイタリア、ヨルダン、カザフスタン、フランスの友人たちと食事をしました。
一番人気な寮は、大学に近く家賃も3~4万ほどで抑えることができます。
自分は市内で生活したいのと友人がその寮にいたのでそこにしました。また、以前の寮は大学から40分と遠いので、冬はかなり苦労すると考えました。ラトビアは天気が変わりやすく、雨と雪とで交通機関が遅れる等は多いようです。
住まい選びはとても大切です。特に自分の場合は、海外の人と住むのは初めてなので安心できる環境を整えることに越したことはありません。値段を安くすれば寮の質は基本的に下がります。特にラトビアはほとんどの建物が古く、ヒーターやベッド等も古い可能性があります。値段は妥協しても、安心感や立地、設備の良さは見込むことができます。
ルームシェアや二人以上で生活する場合は、結局ルーメイトとの関係性が一番大きいかもしれませんが。
友人と話をしていると、多くの人がルームメイトとの生活スタイルの違いで苦労しているようです。寝る時間(電気を消す時間)、部屋で電話をする可能性(騒音)、清潔感(裸足での生活、匂い)等…挙げればきりがないです。
なので、それぞれの基準の確認作業は必要かもしれません。実際、慣れてくる場合もありますが、ストレスがかかることは間違いないでしょう。
自分の場合は、幸いとてもよいルーメイトに恵まれて、毎日楽しく過ごせています。
自分と基準がほとんど同じ感じです。また、伝えるべきことは言い合うようにしています。
以上、ざっと寮の紹介と感想です。自分は現在素晴らしい経験をすることができています。悪条件の中での生活は無理にしようとは思っていないので良い決断だったと思います。
今回も読んでいただきありがとうございました!
人文社会科学部経済学科(Faculty of Engineering Economics and Management) 小林