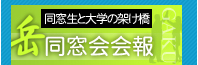こんにちは! 学生レポーターの小林です。
リガはすっかり寒くなってきました。
日中でも10℃くらいしかないので、コートを着始めています。来週は氷点下まで行くようです。今でもたまに氷の粒が降ってきますが。
現地の人たちも同じような格好なので、「やっぱり寒い地域に住んでいても寒いものは寒いんだな」と最近感じました。
さて、今回は自分が選んだ寮の紹介です。
なぜかというと、最近引っ越しをしたからです。
海外の大学へ留学する場合は、寮に住む、アパート、シェアハウスを探すなどいろいろあると思いますが自分は大学が提供している寮に住んでいます。
自分の心構えとしては、「2人以上と生活できる」、「共同のスペース(キッチンや談笑場など)がある」場所に住みたいと思っていました。
1. 以前の寮
もともとは大学、市内からバスで40分ほどの場所にあった寮にいました。
1960年代に建てられたようなので、全体的にかなり古いです。
私からしたらキッチンやバスルームはきれいではなく1年間過ごすのは大変だなと思っていました。(結局1か月ほどしか滞在しませんでした。)
二人部屋で、家賃は3万5000千円程度、水道光熱費、冷蔵庫、シーツが含まれています。
ウクライナとインドからの生徒が大部分を占めているような状態でした。
5階建ての建物で一つのフロアに30部屋ほどあります。
また、1フロアにキッチン、洗面台、トイレが2つずつあります。シャワールームは1階にあって、一度に10人くらいが使えます。
2. 現在の寮
こちらの寮は市内にあります。
1、2、3人部屋が選べて、部屋に人が少なくなるほど家賃が上がっていきます。
自分は2人部屋に住んでおり、オランダ人のルームメイトがいます。
家賃は5万円ほどです。寮内の設備は新しく、水道光熱費、冷蔵庫、シーツが家賃に含まれています。シャワーとトイレ、洗面台が各部屋にあるのが以前の寮との違いです。また、キッチンは10人くらいが使うと思いますが、テーブルがあるのでいろいろな人と話ができます。実際引っ越して2日目にはイタリア、ヨルダン、カザフスタン、フランスの友人たちと食事をしました。
一番人気な寮は、大学に近く家賃も3~4万ほどで抑えることができます。
自分は市内で生活したいのと友人がその寮にいたのでそこにしました。また、以前の寮は大学から40分と遠いので、冬はかなり苦労すると考えました。ラトビアは天気が変わりやすく、雨と雪とで交通機関が遅れる等は多いようです。
住まい選びはとても大切です。特に自分の場合は、海外の人と住むのは初めてなので安心できる環境を整えることに越したことはありません。値段を安くすれば寮の質は基本的に下がります。特にラトビアはほとんどの建物が古く、ヒーターやベッド等も古い可能性があります。値段は妥協しても、安心感や立地、設備の良さは見込むことができます。
ルームシェアや二人以上で生活する場合は、結局ルーメイトとの関係性が一番大きいかもしれませんが。
友人と話をしていると、多くの人がルームメイトとの生活スタイルの違いで苦労しているようです。寝る時間(電気を消す時間)、部屋で電話をする可能性(騒音)、清潔感(裸足での生活、匂い)等…挙げればきりがないです。
なので、それぞれの基準の確認作業は必要かもしれません。実際、慣れてくる場合もありますが、ストレスがかかることは間違いないでしょう。
自分の場合は、幸いとてもよいルーメイトに恵まれて、毎日楽しく過ごせています。
自分と基準がほとんど同じ感じです。また、伝えるべきことは言い合うようにしています。
以上、ざっと寮の紹介と感想です。自分は現在素晴らしい経験をすることができています。悪条件の中での生活は無理にしようとは思っていないので良い決断だったと思います。
今回も読んでいただきありがとうございました!
人文社会科学部経済学科(Faculty of Engineering Economics and Management) 小林
こんにちは! 学生レポーターの小林です。
今回は、先週末行ってきたĶemeru Nacionālais parks(ケメリ国立公園)をレポートします。
リガからは多くの場所にバスや電車が出ているので、移動は大変便利です。
前回のレポートにJūrmala(ユールマラ)の写真があったと思いますが、ケメリ国立公園はユールマラの西側にあります。

リガから電車に1時間ほど揺られ国立公園に到着しました。
しばらく森の中を歩いた後、広大な湿地帯に出ます。このような国立公園は初めて行ったのでとてもいい経験でした。
1000年前にバルト海が後退して形成された湿地帯で、ボードが設置されているのでその上を歩き公園内を一周します。

天気も良く、暖かくとても気持ちのいい周遊でした。1時間ちょっとで回ることができたと思います。
苔や隆起した湿地、沼地、移行湿地。 大ケメリ湿原は、この種の沼としてはラトビア最大の湿地の 1 つです。レッドブックに記載されている保護植物たちも生息しています。


見ての通りとても穏やかな週末になり、リラックスできました。友人たちとも交流もたくさんでき、本当に充実しています。学業も観光もイメージ通り進んでおり、ポジティブに生活できています。
これからラトビアはだんだん日が短くなっていき、寒くなっていきます。まあすでに長袖を来ていますが。今後は学業関係ももっと載せたいと思っています。
お楽しみに!
人文社会科学部経済学科(Faculty of Engineering and Management) 小林
こんにちは!学生レポーターの小林です。
ラトビアに到着し、2週間ほどたちました。
友達もでき、たくさん文化交流ができています。トルコ、ウクライナ、イタリア、ボスニア、フランス、ドイツ、インド、カナダなど、いろいろな人たちと話ができます。
みんな各国の課題や誇るところを知っていて、伝える術を持っています。
いろいろな違いを経験することで日本の良いところ、改善するところも見えてきているような気がします。
ちなみに、静岡大学はまだ夏季休暇中だと思いますが、リガ工科大学は先週から講義が始まりました。留学生用の授業はすべて英語で行われます。
大変ですが、講義内容は非常に楽しく魅力的なものなので頑張っていきたいと思います。
さて、今回はラトビアの写真を載せていきます。説明は短めにしますので、写真をお楽しみください!


リガ ブラックヘッドハウス リガのシンボルですね。夕方は本当に美しい景色です。
ストリートミュージシャンの演奏も聞くことができます。

リガ旧市街のパブ ウェールズ対ラトビア フットボールの試合があったようで盛り上がってました。こんなきれいな景色も毎日見ることができます。

リガ大聖堂 1211年に元の聖堂が建設され、現在の姿になったのは18世紀ごろだそうです。


ラトビアはバスケットワールドカップで5位になりました。パブリックビューイングなども頻繁に行われています。

リガを出てJūrmalaというビーチへ。ウクライナからの留学生と一緒に行きました。電車にも乗りましたが、古めで映画に出てきそうな雰囲気の良さでした。
リガ市以外の場所にもたくさん行きたいと思います。
ラトビアは歴史的な建造物が非常に多いです。かなり古い建物も普通に国民の住居として使われていたりします。日本やRTUのキャンパスのようなモダンな建物は少ない印象です。
それからラトビアはとても平穏で落ち着いた国です。外に出てもリラックスして観光できます。
これから講義も文化交流も機会をどんどん増やして充実した生活を続けたいと思います。
さて、今回も読んでいただきありがとうございました。
人文社会科学部経済学科(Faculty of Engineering Economics and Management)小林
こんにちは!学生レポーターの小林です。
今回はリガに到着しましたのでその報告です。
25日に羽田を出て約13時間かけてイスタンブールへ飛び、

その後イスタンブールから3時間ほどのフライトを経て、リガ国際空港へ着きました。

その後は寮へ行き、手続きを済ませその日は水やトイレットペーパーなどを買って寝ました。やっぱり結構疲れてましたね。飛行機でかなり寝たんですけど。
まずフライトが本当に長かったです。寝てはいましたが、飛行機の中での睡眠などクオリティは非常に低いものとなります。映画やドラマで時間を潰しながら、頻繁に離席してストレッチの連続です。あとかなり寒かった記憶があります。
ラトビアと日本では時差は7時間ほどですので、皆さんが起きる時間くらいにこちらは寝る時間になります。幸い時差ボケもさほどなく、すんなりと環境に溶け込めているような気がします。
それからリガ市内は英語がかなり通じるので全く不便はありません。僕より年代が上の方はラトビア語かロシア語のようです。全く分かりませんが。自分が住んでいる寮の周辺は市内から20分ほどで、年齢層は高めの人が住んでいます。スーパーもコンビニの店員さんもラトビア語ばかりなので、複雑なことはなるべく大学や市内に済ませようと思っています。
ただこちらの人たちはみんな親切ですし、早速ですが楽しめています。

とりあえず今回はこのくらいにします。
リガの情報や近況報告は随時していきますので、お楽しみに!
*私の日本の電話番号は留学中は使いません。そのため、メッセージなどがある方は以下のメールアドレスにお願いします。アドバイスなどなんでも送ってください。
人文社会科学部経済学科(こっちではFaculty of Engineering Economics and Management) 小林
こんにちは!学生レポーターの小林です。
今回は、私の留学についてレポートします。
私は、2023年9月からラトビア共和国にあるリガ工科大学(RTU)に交換留学生として留学します。
RTUでは専門の経済学や経営学を学ぶつもりです。またヨーロッパへ企業訪問に行き、欧州で活躍している人から考え方や働き方などを学んできたいと思います。
学生レポーターの活動については、掲載頻度は不定期となってしまうと思いますが、月に1,2回を目安に続けます。ラトビアだけでなく、ヨーロッパのことをレポートします。お楽しみに!
皆さんラトビアって知っていますか。
ヨーロッパのバルト三国の一つの国です。人口190万人ほどの小さな国で、ラトビア語が話されています。歴史のある国で、調べてみるととても綺麗な街並みを見ることができます。
高校生のころから留学に興味はあったので、大学生になったらどこかに行こうと思っていました。当時は英語圏に語学留学に行こうと思っていた気がします。
しかし、入学と同時にコロナが広まっていった影響で、在学中は無理かなと思ったりもしました。
ただ留学プログラムが再開して現在は、準備を進めています。
自分が思っていた以上に留学に行きたかったようです。(笑)
今は、英語力の向上と日本の魅力の再確認をしています。
向こうに行ったときに話のネタにできるようなものは準備しておきたいという感じです。
今回改めて、応援されると本当に元気出るなと思いました。
僕を応援してくれる人がいて、僕が応援したい人がいることが分かりました。
楽しみながら、多くのことを学んできます。
帰ってきたらお土産も渡しに行くと思います。(笑)
次からは留学についての話になります。お楽しみに。
人文社会科学部経済学科 小林